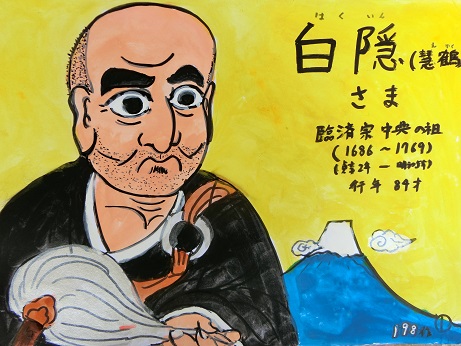
昔、静岡県は[駿河(するが)の国]と呼ばれていました。
こんな歌があります。
「駿河には、過ぎたるものが二つある。富士のお山に、原の白隠(はくいん)」。
白隠さまは、臨済宗の『中興の祖』と呼ばれる立派なお坊さまです。
江戸時代の半ば、駿河の原(はら)宿(今の沼津市)に生まれました。
それでは、白隠さまのお話をさせて頂きましょう。
はじまり、はじまり〜。
白隠さまは、宿場町の大きな運送業の息子として生まれました。
幼き頃の名は[岩次郎]と言い、よく母親と共に近くのお寺にお説教を聴きに行っておりました。
そんなある日のお寺での事。
いつものように、住職がお説教を始めました。
「良いか、悪い事をすれば、あの世で閻魔大王に裁かれて地獄に落ちるんじゃぞ!・・たとえそれが子供であってもな・・、わかったかな。」と話されました。
それを聞いて、岩次郎は心の底から「地獄には行きたくない!」と思いました。
で、悩んだ末・・。
15歳で両親を説得して、出家することにしました。
「よし、私はお坊さんになって、これから一生懸命修行して、必ず極楽へ行かせてもらうぞ!」と誓うのでした。
お坊さんになった岩次郎は[慧鶴(えかく)]と名を改めました。
(が、この紙芝居では悟りを開いたのちの名である[白隠]で通します。)
それから白隠さまの修行の日々は続きます。
朝のお勤め、座禅、掃除、そして托鉢。
それは地獄に行かずに済む、悟りを求めた骨身を削るような修行でした。
そして、良い師匠を求め、全国各地の国を旅して巡り歩きました。
つづく
 [管理用]
[管理用]
記事一覧
※画像をクリックすると拡大されます。
紙芝居:『白隠(はくいん)さま』(その1)
コメント一覧
コメント投稿
- 「名前・コメント」欄を入力し、投稿ボタンを押してください。
